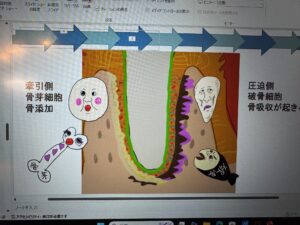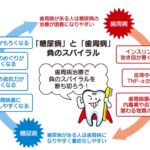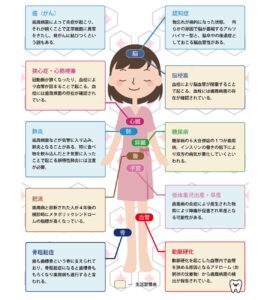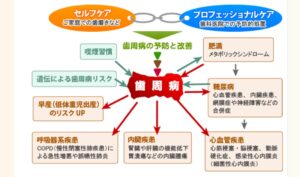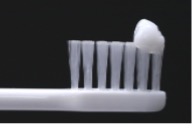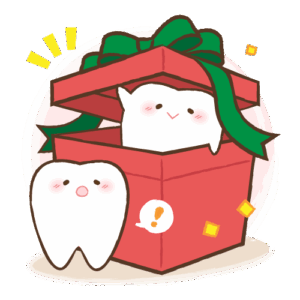みなさまこんにちは、北千住すずらん歯科です🦷🪥
歯並びを改善したい、口元を綺麗に見せたいと思ったこと、ある方も多いですよね。
歯並びを整えたいと考えたとき、多くの方が悩むのが「
どちらも歯並びを改善する治療方法ですが、見た目・

インビザライン矯正とは❓
インビザライン矯正は、
メリット
・透明で目立ちにくく、矯正していることがほとんど分からない
・取り外しが可能なため、食事や歯磨きがしやすく衛生的
・金属を使用しないため、口内炎や金属アレルギーの心配が少ない
・通院回数が比較的少なく、忙しい方にも向いている
デメリット
・1日20〜22時間以上の装着が必要で、自己管理が重要
・複雑な歯の移動や重度の不正咬合には適応できない場合がある
・装着時間が短いと治療が計画通りに進まない
・症例によってはワイヤー矯正より費用が高くなることがある
ワイヤー矯正とは❓
ワイヤー矯正は、歯にブラケットと呼ばれる装置を装着し、
メリット
・幅広い症例に対応でき、難しい歯並びでも治療可能
・装置が固定式のため、装着時間を気にする必要がない
・歯の動きが確実で、治療計画が立てやすい
・インビザラインより費用を抑えられる場合がある
デメリット
・装置が目立ちやすく、見た目が気になる
・食べ物が詰まりやすく、歯磨きが難しい
・装着初期や調整後に痛みや違和感が出やすい
・金属により口内炎ができやすいことがある
インビザラインとワイヤー矯正の大きな違い
最大の違いは「見た目」と「取り外しができるかどうか」です。
インビザラインは審美性に優れ、日常生活への影響が少ない一方、
ワイヤー矯正は見た目の制限はあるものの、確実性が高く、

どちらが自分に合っている?
「目立たずに矯正したい」「仕事や人前に立つ機会が多い」
一方で、「歯並びの状態が複雑」「確実に治したい」「
矯正治療は見た目だけでなく、
どちらの矯正方法が適しているかは、
北千住すずらん歯科では、随時矯正相談のご予約を承っております🪥🦷
矯正治療を行うかどうか迷っている段階の方でも、まずは無料相談・シュミレーションを受けてみませんか❓


https://www.suzuran-dc.net/periodontal/

https://www.suzuran-dc.net/prevention/



https://apo-toolboxes.stransa.co.jp/user/web/06b222c52e4e49cdd1f3cf4b5130bab8/reservations